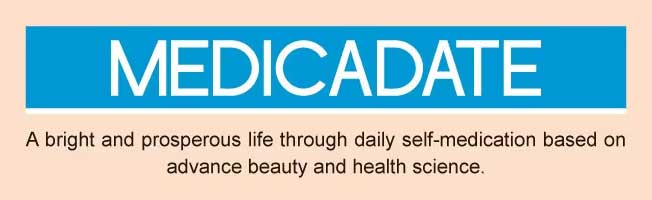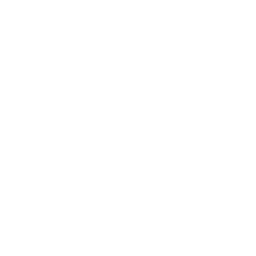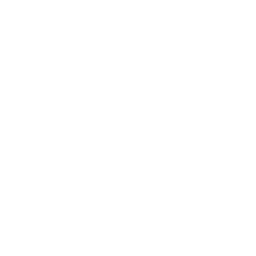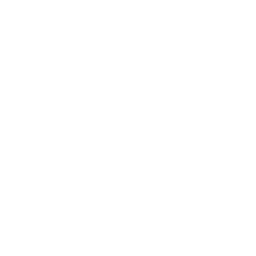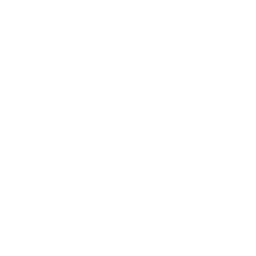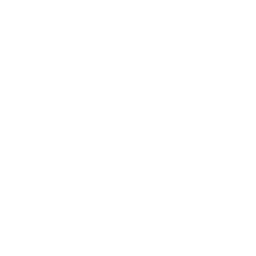カルシウムのすべて!効果的な摂取方法、食品、サプリメントまで徹底解説
毎日忙しく、食事も適当になりがちな現代人の食生活によって、カルシウムが不足している人は少なくありません。しかし、カルシウム不足は、骨粗鬆症や骨折といった深刻な問題につながる可能性もあるため、注意が必要です。
この記事では、カルシウムの基礎知識や効果的な摂取方法・サプリメント選びのポイントなどを分かりやすく解説します。
ぜひこの記事を参考に、カルシウム摂取について見直してみてください。
カルシウムの基礎的な3つの働き
カルシウムは、骨や歯の主成分として広く知られていますが、体の機能を維持するうえで、以下のようなさまざまな役割を担っています。
- 骨や歯の形成と維持をサポートする
- 筋肉の収縮や神経伝達をスムーズにする
- 血液凝固作用に関与する
この章では、カルシウムの基礎的な働きについて、詳しく見ていきましょう。
骨や歯の形成と維持をサポートする
骨や歯の主要な構成成分であるカルシウムは、骨を強く健康に保つために欠かせません。カルシウムを十分に摂取すれば、骨密度を維持し、骨粗鬆症や骨折といったリスクを低減する効果が期待できます。
特に、成長期の子どもたちにとって、カルシウムは丈夫な骨や歯を作る重要な栄養素の一つです。不足すると将来的な健康に悪影響を及ぼす可能性があるので、子どもの成長期には、意識的にカルシウム摂取を促しましょう。
筋肉の収縮や神経伝達をスムーズにする
筋肉の収縮に関わるカルシウムイオンの働きがスムーズに行われないと、けいれんや収縮力の低下が起こる可能性があります。また、神経伝達物質の放出にも関与しているので、神経系の正常な働きを維持するためにもカルシウムは欠かせません。
カルシウム不足によって、筋肉のけいれんや疲労感・神経の過敏性といった症状を引き起こす可能性があるため、注意しましょう。
血液凝固作用に関与する
血液が凝固する際には、カルシウムイオンが血液凝固因子の活性化を促進する働きをします。カルシウムが不足すると、出血しやすくなったり止血しにくくなったりするリスクが高まってしまうでしょう。
そのため、手術前後の患者さんや怪我をした人には、十分なカルシウム摂取を促す必要があります。
カルシウム不足による3つの症状とリスク
カルシウム不足は、自覚症状がないまま進行することが多く、気づいたときには深刻な状態になっているケースがあります。そのため、日頃からカルシウム摂取に気を配り、不足症状に気を付けておくことが重要です。
ここでは、カルシウム不足が疑われる以下の3つの症状やリスクについて解説します。
- 骨粗鬆症や骨折リスクの増加
- 筋肉のけいれんや疲労感
- イライラや不安感などの精神的な症状
カルシウム不足のリスクを理解し、積極的な摂取を心がけましょう。
骨粗鬆症や骨折リスクの増加
カルシウム不足は、骨密度を低下させ、骨粗鬆症や骨折のリスクを高めます。
骨粗鬆症は、高齢者に多くみられる骨がもろくなって骨折しやすくなる病気のことです。初期段階では自覚症状がないことが多いですが、進行すると骨折しやすくなり、日常生活に支障をきたすこともあるでしょう。
そのため、定期的な骨密度検査を受け、早期発見・早期治療に努めることが重要です。若い世代でもカルシウム不足によって発症する可能性があるので、適切なカルシウム摂取を心がけ、骨の健康を維持しましょう。
筋肉のけいれんや疲労感
カルシウムは筋肉の収縮に欠かせないミネラルの一つです。カルシウムが不足すると、筋肉のけいれんが起こりやすくなってしまいます。また、慢性的なカルシウム不足は、筋肉の収縮機能の低下から、疲労感や倦怠感を引き起こす可能性もあるでしょう。
激しい運動後などに、筋肉のけいれんを感じやすい場合は、カルシウム摂取を見直してみるのがおすすめです。
イライラ、不安感などの精神的な症状
カルシウムは神経伝達にも関与しているため、不足するとイライラしやすくなったり、不安感が強くなったりすることがあります。
また、集中力の低下や睡眠障害なども引き起こす可能性もあるので、精神的な症状に悩んでいる場合は、カルシウム摂取について医師にアドバイスを受けるのもおすすめです。心身の健康維持のためにも、カルシウムを適切に摂取しましょう。
1日に必要なカルシウム摂取量
厚生労働省が発表している「日本人の食事摂取基準」による1日に必要なカルシウム摂取量の目安は、以下のとおりです。
| 性別 | 年齢 | 目安摂取量(1日あたり) |
| 男性 | 18〜29歳 | 約800mg |
| 30〜74歳 | 約750mg | |
| 75歳以上 | 約700mg | |
| 女性 | 18〜74歳 | 約650mg |
| 75歳以上 | 約600mg |
ただし、妊娠・授乳期には、胎児や乳児の骨格形成のために、通常の摂取量よりも多くのカルシウムが必要です。
また、高齢期は、骨粗鬆症予防のため、積極的にカルシウムを摂取することが推奨されています。
カルシウムを多く含む食品
カルシウムを効率良く摂取するには、以下のような食品からバランスよく摂るのが重要です。
| 食品 | 詳細 |
| 乳製品 | ・牛乳 ・ヨーグルト ・チーズ |
| 魚介類 | ・小魚 ・しらす ・煮干し |
| 緑黄色野菜 | ・ほうれん草 ・小松菜 |
| 豆類 | ・豆腐 ・納豆 |
ただし、シュウ酸やフィチン酸を含むほうれん草などは、カルシウムの吸収を阻害する可能性があるため、注意が必要です。
カルシウムサプリメントの選び方のポイント
カルシウムサプリメントは種類が多く、どれを選べば良いか迷う人も多いと思います。 効果的にカルシウムを補給するためのサプリメント選びのポイントは、以下のとおりです。
- 吸収率の良いカルシウムを選ぶ
- 添加物や成分表示を確認する
- 信頼できるメーカーから購入する
ポイントを押さえて、自分に合った効果的なサプリメントを選びましょう。
吸収率の良いカルシウムを選ぶ
吸収率が良いカルシウムを選ぶことで、少ない摂取量でも効率的にカルシウムを補給することが可能です。たとえば、 一般的に、乳酸カルシウムやクエン酸カルシウムは吸収率が良いとされています。
含有量にも注目して、必要なカルシウム摂取量に合ったサプリメントを選びましょう。
添加物や成分表示を確認する
添加物が少ないサプリメントを選ぶことで、体への負担を軽減できます。
成分表示をよく確認し、アレルギー物質が含まれていないかをチェックするのも重要です。自分がアレルギーを持っている成分が含まれていないか、しっかりと確認しましょう。
信頼できるメーカーから購入する
サプリメントは、健康に直接関わるものなので、信頼できるメーカーから購入するのがおすすめです。大手メーカーや信頼できるブランドの製品を選ぶことで、品質と安全性を確保できます。
「MEDICADATE」は、有名な成分や売れている成分などではなく、「科学的に効果があること」にこだわり、世界中からエビデンスの確かな原料のみを厳選しているのが特徴です。
先進の社会学・健康寿命学のエビデンスに基づいた製品開発をしているので、安心と結果を感じやすいでしょう。
カルシウムの吸収を促進する栄養素と食べ合わせ
カルシウムの吸収率を高めるためには、ビタミンDとの組み合わせが効果的です。以下の食材には、ビタミンDが多く含まれています。
- 鮭やマグロなどの魚介類
- 卵黄
- きのこ類
また、マグネシウムもバランスよく摂取することで、吸収率を高める効果が期待できます。 マグネシウムを多く含む食材は、以下のとおりです。
- ナッツ類
- 大豆製品
- ほうれん草
一方、シュウ酸やフィチン酸を多く含む食品(ほうれん草、ひじきなど)は、カルシウムの吸収を阻害する可能性があるため、注意しましょう。
カルシウム摂取の注意点
カルシウムは大切な栄養素ですが、摂取方法や量によっては体に悪影響を及ぼす可能性もあります。 カルシウム摂取の注意点は、以下のとおりです。
- 過剰摂取を防ぐ
- サプリメントは空腹時の摂取は避ける
- 不安なことは専門家へ相談
注意点を理解して、過剰摂取を防ぎましょう。
過剰摂取を防ぐ
カルシウムは体に必要な栄養素ですが、過剰摂取すると、腎結石のリスクが高まる可能性があります。尿中にカルシウムが結晶化して腎結石になってしまうと、激しい痛みを引き起こすため、1日の摂取上限量を守らなければなりません。
適切な摂取量は、健康状態に合わせて、医師や栄養士に相談しましょう。
サプリメントは空腹時の摂取を避ける
サプリメントは、空腹時に摂取すると胃腸への負担が大きくなる可能性があります。食事と一緒に摂ることで吸収率を高められる傾向にあるため、空腹時の摂取は避けましょう。
また、他の薬との相互作用がないかを確認するのも重要です。服用中の薬がある場合は、医師や薬剤師に相談してみてください。
不安なことは専門家に相談カ
カルシウム摂取について不安なことがあれば、医師や栄養士に相談するのがおすすめです。専門家のアドバイスを受けることで、年齢や健康状態に合わせた適切な摂取方法や量が明確になります。
必要に応じて、血液検査などでカルシウムの状態も確認できるので、健康に関する不安がある場合は、専門家に相談しましょう。
健康のために賢くカルシウムを摂ろう
カルシウムは骨や歯だけでなく、筋肉や神経・血液凝固にも欠かせない栄養素の一つです。
不足すると骨粗鬆症や骨折・筋肉けいれん・精神的な不安定などを招く可能性があるので注意しましょう。牛乳・ヨーグルトなどの乳製品や小魚・緑黄色野菜など、カルシウムを多く含む食品を摂取するのがおすすめです。
過剰摂取や薬との飲み合わせが不安な場合は、医師や栄養士に相談のうえ、適切なカルシウム摂取を心がけてみてください。